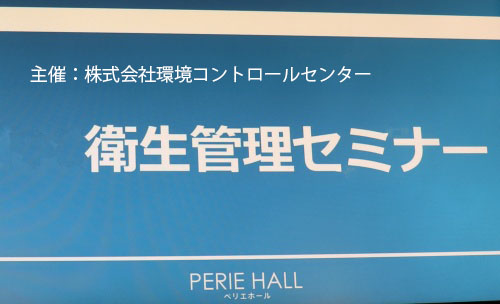自宅でアリガタバチ発生!!

見に行ってみると、朝日に照らされ、体長1㎜ほどの黒いハチがいました。
このシルエットは・・・「アリガタバチ」だ!!
このサイズのアリガタバチというと、シバンムシに寄生するシバンムシアリガタバチがまず思い浮かび、他にハチがいないか、子どもたちが刺されていないかすぐにチェックしました。幸い、子どもたちに被害はありませんでしたが、なぜ家の中にいたのでしょう。シバンムシを見かけたこともないのに。とりあえず見つけたアリガタバチを捕獲し、会社で調べました。
と、冒頭から「アリガタバチ」という名前を出しましたが、ご存じない方にはどんな虫なのかわからなかったと思います。申し訳ありません。ここで、アリガタバチについて簡単にご説明します。
〔目次〕
1.アリガタバチとは
2.人に皮膚炎を起こすアリガタバチ
①シバンムシアリガタバチ ②クロアリガタバチ ③ノコギリヒラタアリガタバチ
④キアシアリガタバチ
3.対策
①食品の管理 ②清掃 ③隙間処理
④フェロモントラップによる捕獲 ⑤殺虫剤の使用
1. アリガタバチとは
アリガタバチは、「アリ」とついているように、外見がアリに似たハチの仲間です。アリもハチの仲間ですが、アリは胸部と腹部をつなぐ節(腹柄)があることで区別できます。アリガタバチ、正式には、ハチ目のアリガタバチ科Betylidaeの総称です。日本には80種以上のアリガタバチが生息しています。
雌は無翅で、雄は有翅ですが、雌でも翅のあるもの、雄でも翅のないものもいます。体長は1~5㎜程度の種が多く、体は黒色をしているものがほとんどです。雌は産卵管が毒針の役目をしています。一方、雄は毒針はないので、刺すことはありません。
アリガタバチは寄生蜂で、主にチョウ目やコウチュウ目の昆虫の幼虫に寄生します。寄主となる虫の幼虫や蛹に産卵管を刺し、麻痺させて卵を産みつけます。孵化した幼虫は寄主を栄養にし成長していきます。
2. 人に皮膚炎を起こすアリガタバチ
アリガタバチは前述したように、他の虫に寄生する蜂です。しかし、屋内で発生し、誤って人間を刺すことがあります。刺された時はチクッとした軽い痛みですが、何度か刺されるとアレルギー反応を起こし、痒みを伴う赤い腫れを生じます。稀にアナフィラキシーショックを起こすこともあるそうです。冒頭に書いたシバンムシアリガタバチもその一つです。食品害虫であるタバコシバンムシやジンサンシバンムシに寄生します。
ここで、屋内で発生し、人を刺す恐れのある注意すべきアリガタバチを紹介します。
①シバンムシアリガタバチ
食品害虫であるジンサンシバンムシやタバコシバンムシに寄生します。
シバンムシアリガタバチ(雌)

ジンサンシバンムシ

タバコシバンムシ
②クロアリガタバチ
シバンムシ類やカミキリムシ類、ナガシンクイムシ科などの幼虫に寄生することが知られています。カミキリムシ類やナガシンクイムシ類は木材や竹等を加害する種類です。
③ノコギリヒラタアリガタバチ
食品害虫であるノコギリヒラタムシの幼虫に寄生します。被害例は少ないとされています。
ノコギリヒラタムシ
④キアシアリガタバチ
食品や衣類を食害するヒメマルカツオブシムシの幼虫に寄生します。被害例は少ないとされています。今回、筆者の自宅で発生したのは、このキアシアリガタバチでした。確かにヒメマルカツオブシムシの幼虫は時々目撃していました。

キアシアリガタバチ(雄)

ヒメマルカツオブシムシ(成虫)

ヒメマルカツオブシムシ(幼虫)
3.対策
アリガタバチは寄生蜂ですので、寄主がいなければ発生することはありません。つまり、寄主を発生させない対策が大切です。ここでは特に被害の多いシバンムシアリガタバチの寄主を中心とした対策を紹介します。①食品の管理
寄主として挙げたシバンムシ類、ノコギリヒラタムシは穀類や穀粉、菓子類などの加工食品、ペットフードなどから発生します。これらを開封した状態で保管しておくと、食害されやすくなります。開封した食品は密閉容器で保管するようにしましょう。②清掃
食品屑を溢したままにしておくと、様々な虫が発生、誘引されます。また、タバコシバンムシは畳から発生することがあり、ヒメマルカツオブシムシは室内の埃等も餌としていますので、定期的に室内を掃除機がけするようにしましょう。その際、棚の下や裏など普段目の届きにくい場所、食品を保管している棚、クローゼット等の清掃にもご注意ください。③隙間処理
網戸のほつれや換気口の隙間から侵入することがありますので、網戸の修繕や換気口への防虫網の設置をしましょう。④フェロモントラップによる捕獲
主に工場等では、タバコシバンムシやジンサンシバンムシ、ノコギリヒラタムシ、ヒメマルカツオブシムシを特異的に捕獲するトラップを用いて発生状況を監視します。ただし、このトラップは発生状況を監視するためのもので、駆除を目的としていません。⑤殺虫剤の使用
虫を発見・発生しているという時、まずは虫をいなくさせたいという場合には殺虫剤を使うことも有効です。燻蒸式・煙霧式のものや、スプレー式のものを使うとよいでしょう。近年は被害報告も減ってきているようですが、我が家のように発生することがあるかもしれません!
掃除をしっかりやっていればよかった・・・。
日頃から荷物の整理整頓、清掃をするというのは大事ですね。
今回紹介した虫の一部は、害虫情報のページにも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
害虫駆除業務の概要はこちらから
駆除のご依頼、お問い合わせはこちらから