ノシメマダラメイガ
生態と特徴

体長…成虫:開張13~16㎜、体長7~8㎜
幼虫:終齢幼虫で10~12㎜
蛹:6~8㎜
卵:長径0.5㎜、短径0.3㎜
体色…成虫:前翅基部側半分は淡黄色、外側半分は濃灰褐色で赤褐色の
斑紋を呈す
幼虫:頭部は茶褐色、胴部は黄白色、老熟すると背面が淡紅色や
淡緑色を呈す
蛹:橙黄色
卵:乳白色
雌成虫は、付着性のある卵を加害物の上に産卵します。
幼虫は大量の糸を吐き、穀粒などをつづって巣を作ります。密度が高い場合は絹糸で覆われたような状態となります。幼虫の糞は餌に関わらず赤褐色の粒状となっていることが、他種と区別できる特徴です。また、発育は餌の種類によって異なり、米や玄米で早く、ついで小麦、大麦、豆類の順となっています。幼虫は、蛹化前や越冬に入る際はよく動き回る傾向にあり、加害物とは関係のない場所で発見されることがあります。
穿孔力が強く、包装材を食い破って食品に侵入することから、食品への異物混入事例が多く報告されています。
分布と発生場所
世界各国に分布し、日本も全国に分布しています。しかし、沖縄での発生例は少ないと報告されています。発生場所としては、一般家庭では食品の置いてある台所、食品工場では貯蔵庫を始め、食品カスやこぼれ落ちた食品が
見られるような場所で発生します。野外では鳥の巣からも発生します。
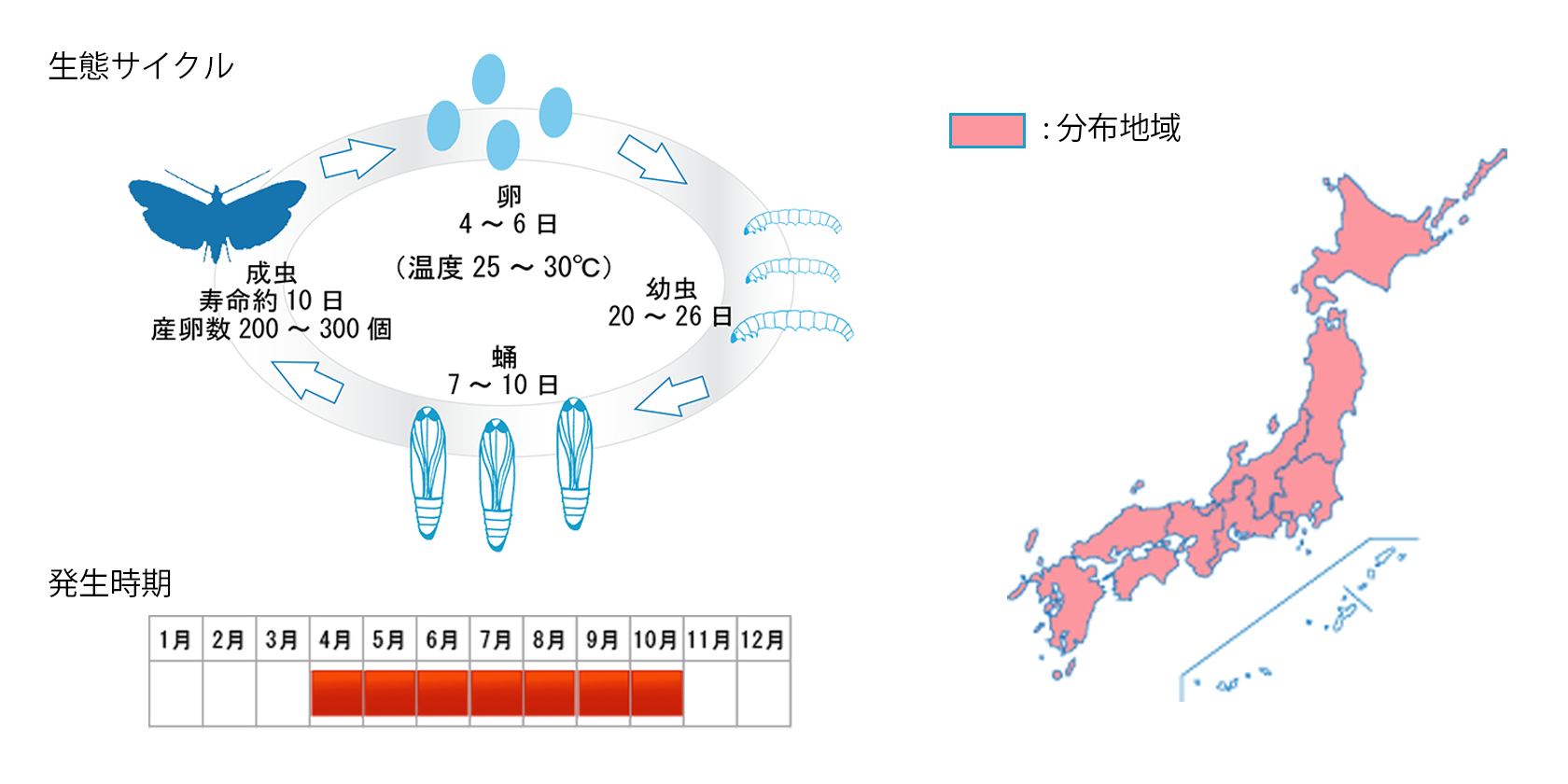
被害
幼虫は各種穀類(米、小麦、トウモロコシなど)とその加工食品、豆類、ナッツ類、ココアやチョコレート、乾燥果実などの食品を食害します。特に、ビスケットやインスタント麺等の油分を多く含む食品を好むとされています。食品以外ではドライフラワーからの発生も確認されております。駆除・防除方法
発生を予防する方法としては、発生しない環境作り、清掃と保管方法が大切です。米びつ等は定期的に清掃すること、食品は密閉容器で保管すること、可能であれば低温(冷蔵庫)で保管するとよいでしょう。さらに、本種に対してはフェロモントラップが開発されているため、設置することで捕獲と発生状況を確認することができます。発生が確認され薬剤処理を実施する場合には、くん蒸やエアゾール剤を用いて殺虫し、その後加害された食品は破棄
してください。発生源がわからない場合には専門業者に調査してもらうことをお勧めします。
